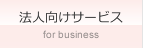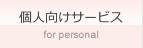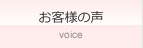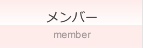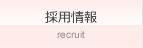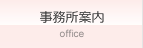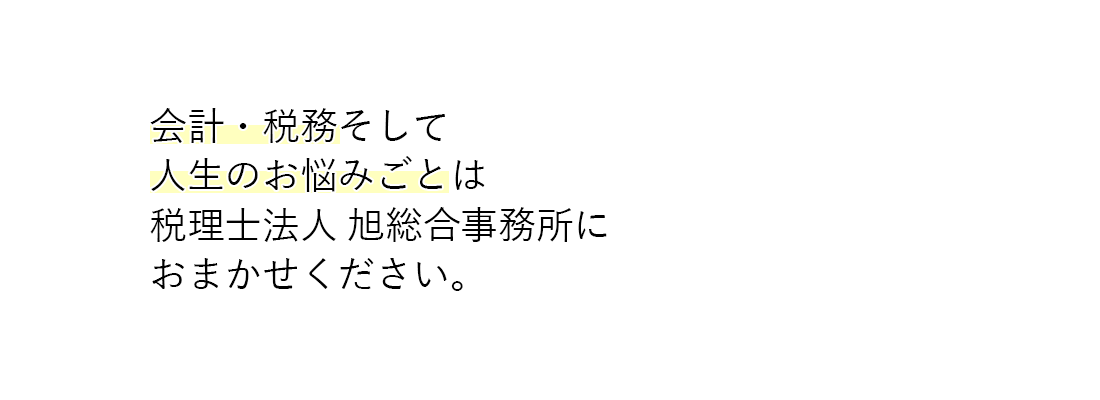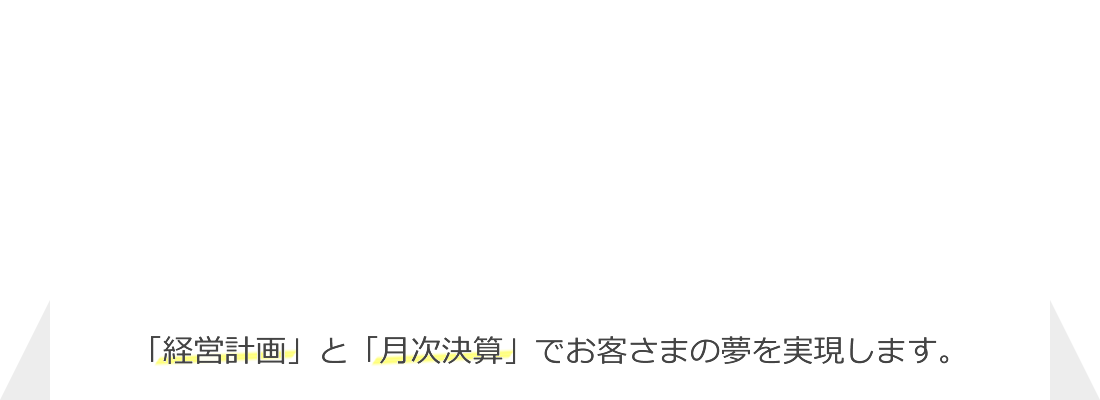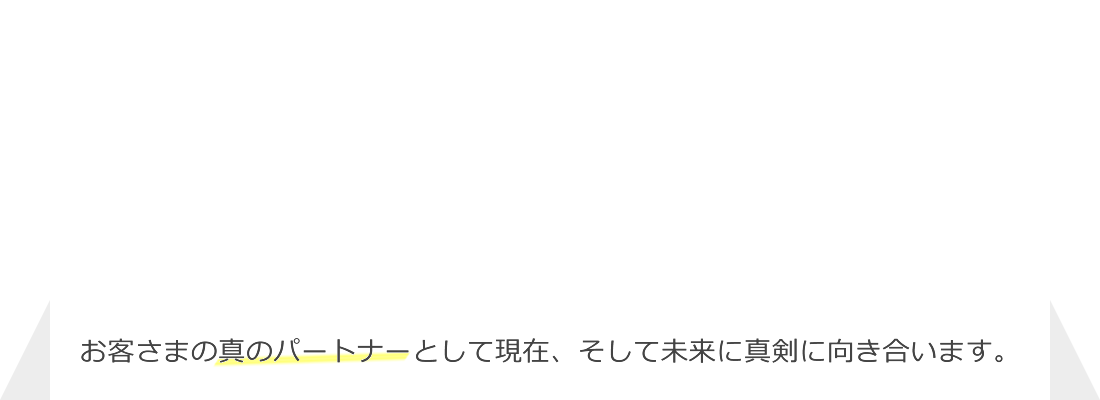6つの特長とこだわり
特長 ①さまざまな経営課題にも共に取り組む

“真のパートナー”として、企業価値最大化のためにお客さまの立場で共に解決策を考えます。
一般的な税理士事務所が行う定型業務だけでは終わりません。
特長 ②お客さま目線 丁寧にご対応

“お客さまにとって”
これを常に考え、さまざまなご提案からお客様が最適解を導き出すようにサービスを行っております。
一方通行型ではない、積極的なアプローチがあります。
特長 ③“わかりやすく”、“早く”経営数値を提示

税理士法人 旭総合事務所では、9ヵ月決算を実施しております。
申告ギリギリまで納税額がわからないことはありません。早めの年間収支予測が立てられるので、節税対策の助言も行っております。
特長 ④税務調査に強い

税務調査に強い税理士が立ち会うことで、余計な税金を課されるリスクを大幅に軽減!
ほかの税理士事務所からも相談されるほどの豊富な経験があります。
特長 ⑤税理士報酬の内訳が明瞭

一般的な税理士事務所のサービス料金には基準がないなかで、税理士法人 旭総合事務所では、お客さまへのヒアリングに基づき、適正料金にて詳細な報酬内訳を提示させていただきます!
特長 ⑥最新のIT技術に詳しい

IT技術に詳しいスタッフが揃っています。
会計システムをIT化したい、といったようなITビジネスにおいて遭遇するさまざまな税制面、ビジネス面を充実したサービスでサポート!